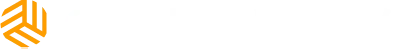市町村が実施する耐震診断の「現地調査」とは?
以前、地震対策の第一歩として、ご自宅の耐震診断を受けてみることをおすすめしました。では、その耐震診断では実際にどのようなことを調査するのでしょうか?今回は、耐震診断における「現地調査」について詳しくご紹介します。
現地調査で確認するポイント
耐震診断を受ける際、各市町村に申し込むと、「木造住宅耐震診断士」の資格を持つ建築士が現状の建物の調査・診断を行います。
調査にかかる時間は通常1~2時間程度。特に重要なのは、以下の2つのポイントです。
- 建物の荷重を安全に支えられているか
- 耐力壁が適切に機能しているか
これらを中心に、建物全体の構造や状態を詳細にチェックしていきます。
現地調査の流れ
1. 床下のチェック

床下に入り、基礎の状態や構造を確認します。具体的には以下のような点をチェックします。
- 基礎の形状
- 土台や床束の状態(腐朽やひび割れがないか)
- 筋かいの金物の有無(しっかり固定されているか)
- 湿気のたまり具合(カビや腐朽の原因になる)
- シロアリ被害の有無
床下は、建物の土台を支える重要な部分です。劣化が進んでいると耐震性に大きく影響するため、細かく確認されます。
2. 天井裏のチェック

次に、天井裏に入り、柱や梁の組み方をチェックします。
- 耐力壁の配置や納まり(適切な位置に設置されているか)
- 柱や梁の接合部の状態(ズレや隙間がないか)
天井裏の構造は普段目にすることがないため、耐震診断の際にしっかりと確認してもらうことが大切です。
3. 屋根や外壁、水回りの確認
耐震性に影響を与える部分として、屋根や外壁の劣化状況もチェックされます。
- 屋根の重さ(重い瓦屋根は耐震性に影響)
- 外壁のひび割れや剥がれ(構造に影響する可能性あり)
- 水回りの劣化(配管の水漏れが基礎に影響を及ぼすことも)
建物の外側や水回りの状態を把握することで、耐震補強の必要性を判断できます。
診断結果の報告と今後の対応
調査後、担当した建築士が調査結果をまとめた診断書を作成し、報告を行います。市町村が実施する耐震診断は、簡易的なものではありますが、大まかな耐震性能の傾向を把握するには十分な指標となります。
もし診断の結果、耐震性に問題があると判明した場合は、補強工事の必要性や具体的な対策について検討することができます。
まとめ
耐震診断は、地震に強い家づくりの第一歩です。市町村が実施する診断を活用することで、建物の現状を把握し、必要な対策を講じることができます。
「うちの家は大丈夫かな?」と不安に感じたら、まずは耐震診断を受けてみることをおすすめします。
設計部 金岡